はじめに
どうもこんにちは!はてなっちでござりまする!今回は、下記内容についてです。
紹介する側として、絶対行っちゃいけないことを言うとするならば
私は本を読むのが嫌いです笑
集中力が本当に持たない人間で、読んでいても、物音だったり、周りの環境だったりが気になってすぐ飽きてしまいます。前の記事でも言いましたが、誰か何とかなる方法知ってたら教えてください笑
ということで、そんな私でも、「あーこれいいなぁ!飽きずに読めるなぁ」と思えた本たちを、紹介をしていきたいと思います。今回もよろしくお願いしまーす!
おすすめの本紹介
1冊目
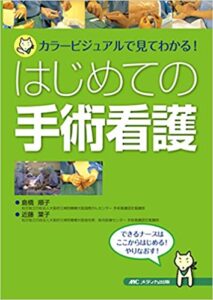
手術室の基礎的な内容について書かれた本です。新人オペ看は必ず買って!と、言っていいほどな、1冊かなと思います。イラスト・写真を多用しており、とても見やすいですし、麻酔、体温管理、体位管理などのテーマ別に看護の手順、観察項目、コツや注意点がのっています!
新人だけでなく、指導者側も、教えるのに役立つ1冊だと思います!全オペ室に置かれるようになればいい1冊かなと個人的には考えています!
2冊目

もうこれに至っては、タイトルの通りです笑
使用薬剤の作用・副作用についてはもちろん、観察ポイントなどもわかるようになるため、是非ともほしい1冊です!こんなこと言ったら、怒られるかもしれませんが、病棟に比べて麻薬・向精神薬・毒薬・劇薬の取り扱いが多く怖い薬、危険な薬ということを忘れがちになります。ですが、こういった本を読み返したり新人に教えたりすることで、改めて大変な薬を使って患者さんの対応をしているんだなということを思い知らされます。
病棟の看護師さんにも、こういった薬を使っているため、術後に”こういう症状がでるかも”と予見できるので、是非是非読んでほしい1冊です。
3冊目

器械出しはもちろん、外回りにも使える1冊です。学生時代に勉強して、国家試験前にもやったんですが、まぁ大体と言っていいほど、するするーと、抜けていってしまうのが解剖ですよね笑 勉強していないと、「大体あんなんだったなぁ~」といった感じで、曖昧になりますが、イラストと画像で分かりやすく知識の再定着をしてくれる、基本的な1冊になります!
検査画像も載っているため、解剖以外の勉強にも、もってこいです!是非読んでみてください!
4冊目

これに至っては少し踏み込んだ本になりますかね?麻酔科の研修医が持っているイメージのある本です。いままでは、”状態がよくない”ことを、報告しかできなかったことに対して、この本で知識を付けることによって、自分で状況から推測し、”こうすればいいんじゃないか?”という考えに、持っていくことができるようになる1冊かなと思います。
1歩踏み込んだ知識を付けたいと考えてるオペ看に、ぜひ欲しい1冊かなと思い、載せてみました!
5冊目

資格取得のためのテキストです。周術期管理チーム認定制度という、術前・術中・術後(周術期)における基礎的な教育を受けたことを証明する第一歩となる資格です。これについて自分は、受験資格も得て、試験を受ける直前まで行ったのですが、新型コロナのせいで、病院の方針で、たとえ試験のためでも県外に出るのがダメ!となってしまい、結局受けずじまいでした。ですがオペ看は持っていて損はない1冊です!
私が持っているのは2016年刊行の第3版なのですが2021年に第4版が出たので興味ある方は是非新しいの買って見てみてくださいね!!
+αとして…

言わずも知れた病気が見えるシリーズです。”病みえ”的な略し方をされていていると思いますが、学生の頃は医学部の学生が試験勉強や国試対策に使ってて、看護師が見るイメージはありませんでした。まず病棟に配属され、先輩に「お勧めだよ!」と言われ買ってみたのですが、病棟・オペ室に勤務する看護師はもちろん、看護学生にも絶対に買ってほしい本だと思いました。疾患と、解剖・生理をイラスト・写真・図表・グラフなどで解説され、症状に対しての対応もあり、いいなと思います。
オペ看として働いていると、疾患や解剖整理に対する理解の部分が、おざなりになってしまうと思っているので、まずは、興味がある科の本を読んで、知識や対応力を付けるのはいいのかと思っています。
ということで、お勧め本紹介でした!
おわりに
飽くまでも、自分が見た中で「いいな!」と思った本なので、これもお勧めだよ!これの方がまとまってて良いよ!というような物がありましたら是非教えてください!これ以外にもいい本はもちろんあるとおもいますので是非是非、時間を見つけて書店とかに行ってみてくださいね!
今回はここまでになります!次回もまた是非読んでくださいね~!




